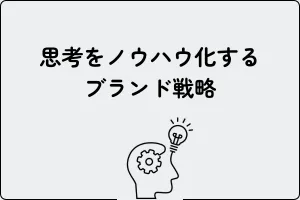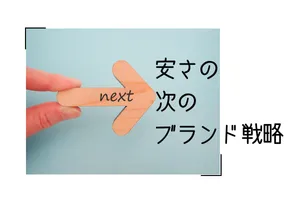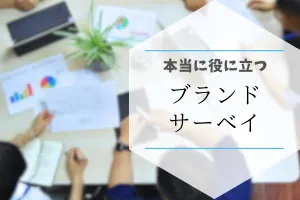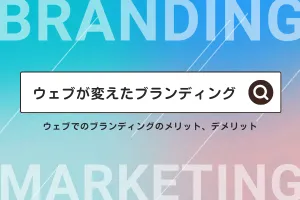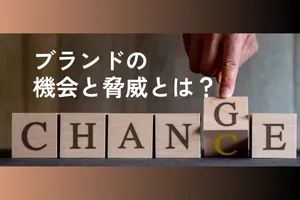「ブランド戦略における「現実歪曲力」とは?
顧客体験の水準を下げない意思決定の秘訣
配信日:2026年2月18日
企業の意思決定は、ほぼ例外なく「合理性」に支えられています。説明がつくこと、前例があること、そして失敗のリスクが低いこと。これらは経営において極めて正しい判断の積み重ねです。
しかし、この「合理性」が過剰に積み重なったとき、皮肉にもブランドの品質は低下し、体験は業界平均で止まり、妥協は「現実解」という言葉ですり替えられてしまいます。誰も手を抜いておらず、誰も間違っていないはずなのに、知らず知らずのうちにブランドの「手触り」が劣化していく。このような事態は、多くの企業で静かに進行しているのではないでしょうか。
効率化の裏に潜む「顧客体験(CX)」低下の罠
レストランにおけるサービス水準の変化
最近の飲食店を思い浮かべてみてください。注文はQRコード、お水はセルフサービス。店員の方は奥に控え、こちらから呼ばない限り声がかかることはありません。
これは決してサービスの放棄ではなく、人手不足やコスト管理、回転率向上を追求した「合理的な判断」の結果です。しかし、その積み重ねによって「お客様の様子を見てお声がけする」といったかつての当たり前は、いつの間にか“特別なサービス”へと格上げ(あるいは市場から消失)されました。知らないうちに「最低ライン」が下がっていく、これがブランド劣化の典型例です。
カスタマーサポートが直面する「合理性」の限界
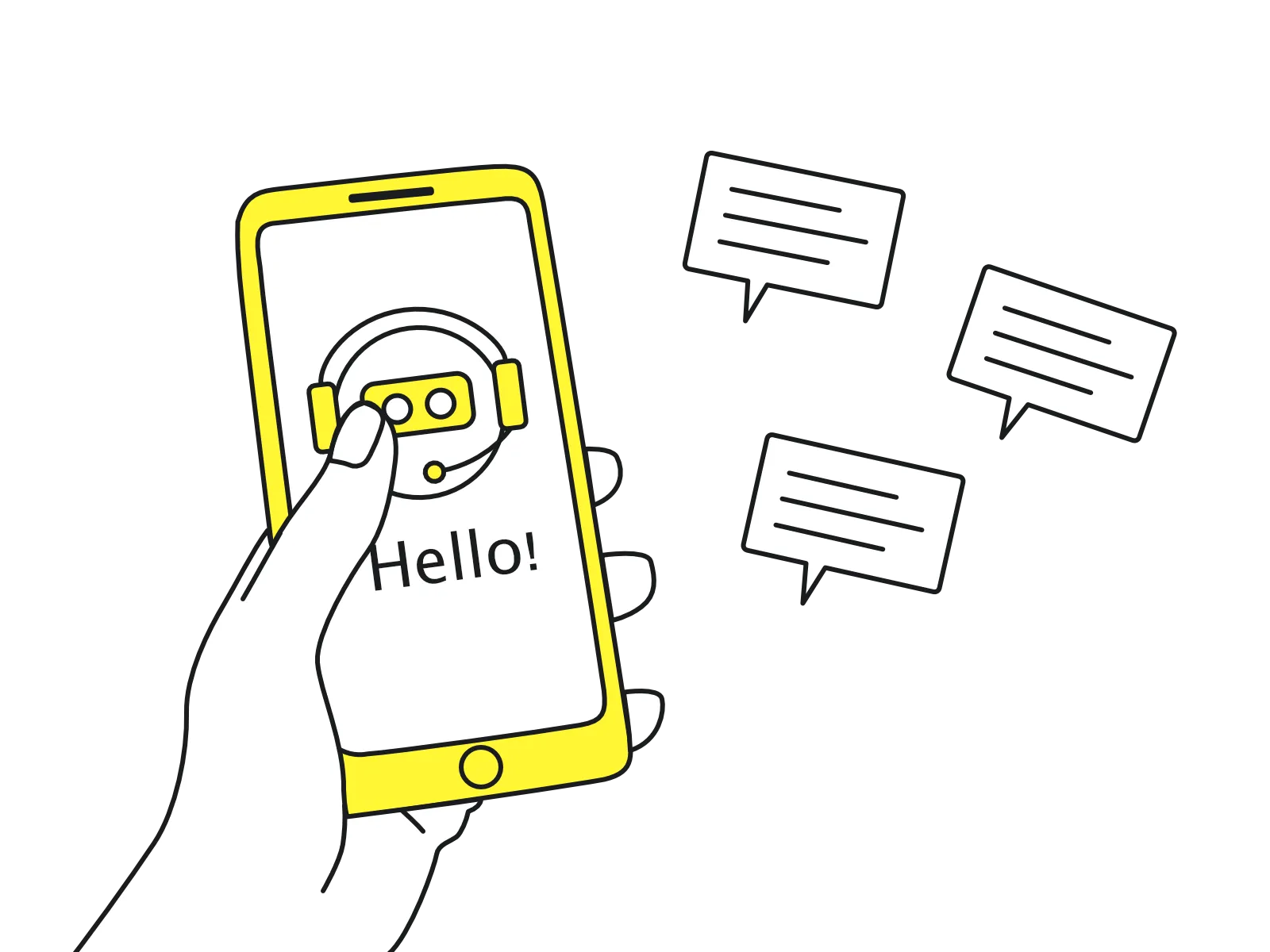
ECサイトやITサービスのサポートも同様です。FAQへの誘導、チャットボットによる一次対応、想定外の事態には「規定のページをご覧ください」という堂々巡り。
業者側にとってはコスト削減として完全に合理的であり、誰も怠けてはいないのでしょう。しかし、結果としてユーザーは自ら解決策を「探索」する負担を強いられます。「困ったら助けてくれる」という安心感は、「正しい手順を踏まない限り対応してもらえない」という条件付きの体験に置き換わってしまいました。
スティーブ・ジョブズに学ぶ、ブランド構築の思考法

ここで対照的な存在として、スティーブ・ジョブズを挙げたいと思います。彼を語る際によく使われる「現実歪曲力」という言葉があります。これは単に現実を無視する力ではありません。彼が歪めたのは現実そのものではなく、人々が現実を見ようとする際の「当たり前の水準(スタンダード)」だったのです。
「判断順序の操作」がブレイクスルーを生む
iPhoneの開発初期、キーボードやスタイラスペンが常識だった時代に、ジョブズは「指によるタッチパネル」を絶対条件に据えました。当時の技術水準では、誤操作やコストの面から「非合理的だ」という反論がいくらでもあったはずです。しかし彼は可能性を議論するのではなく、先に「水準」を決めてしまいました。
するとチームには、技術的な進化以上の変化が起きました。評価基準が変わり、議論の前提が変わり、注意の向きが揃ったのです。チームは「できるか、できないか」を悩むのをやめ、「どうすればこの水準を実現できるか」だけを考えるようになりました。これこそが、ブランドが現実を塗り替える瞬間の正体なのです。
ブランドの「当たり前」を高め続ける組織へ
組織の判断を分解すると、多くの場合「制約(現実)を見る」→「可能な範囲を見積もる」→「行動を決める」という順序を辿ります。この構造では、判断の起点が常に「できない理由」に置かれてしまいます。ブランド戦略として「現実歪曲力」を応用するならば、この認知の順序を意図的に組み替える必要があります。
- 「あるべき水準」を最初に定義する。
- それを「当然満たすべき前提」として扱う。
- 議論の焦点を「実現方法の探索」に固定する。
「無理かもしれない」という選択肢を最初から注意の外に置くことで、組織の学習能力は最大限に引き出されます。そして、その高い水準への挑戦を評価し、称える文化を醸成することがコツです。そして品質やサービスの水準が、一段高いところで安定し始める時、それは「選ばれるブランド」としての矜持が確立されます。