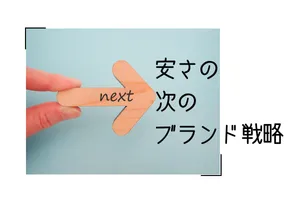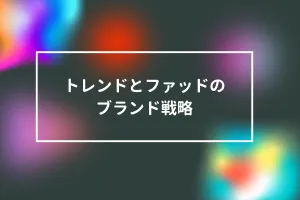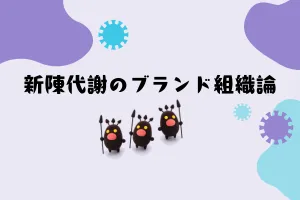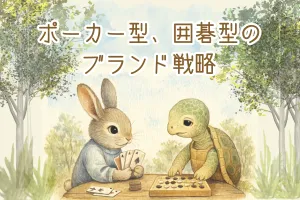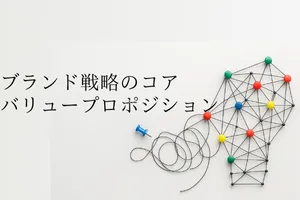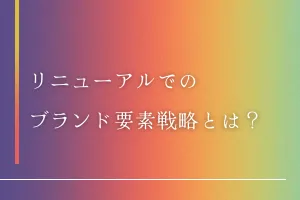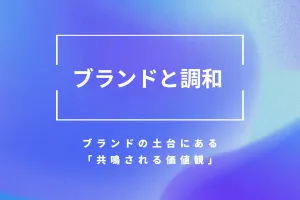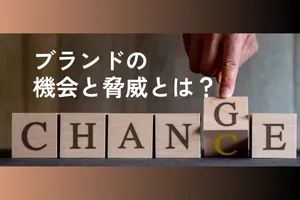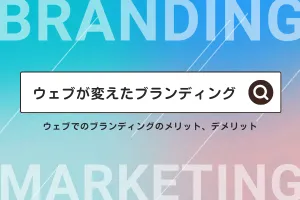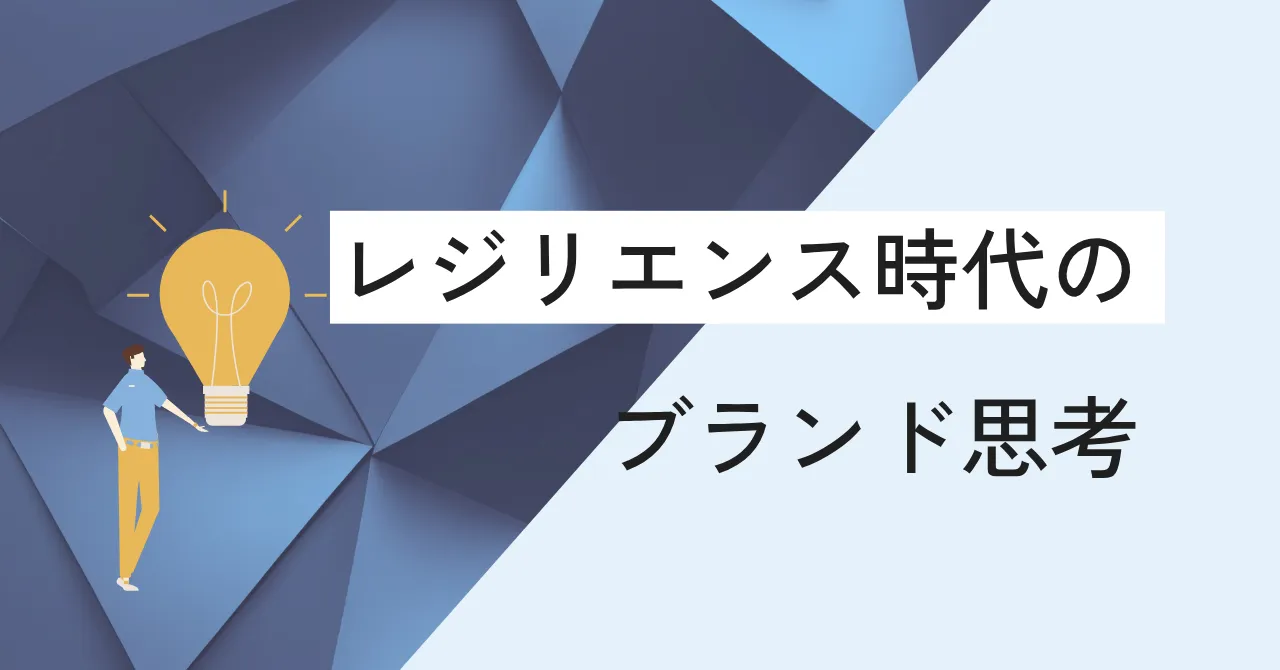
レジリエンス時代のブランド思考
配信日:2025年6月18日
最近、「レジリエンス」という言葉を耳にします。企業でも個人でも、「しなやかに耐える力」が求められるようになりました。しかし、あまりにも「レジリエンス、レジリエンス」と言われると、どこか、前向きな力というより「我慢」や「粘り強さ」ばかりが強調されているようにも感じます。
レジリエンス時代=四重苦の時代
今の日本は、まさに「四重苦」とも呼べる状況です。ひとつ目は、原材料コストの高騰。円安の影響で、あらゆるものがじわじわと値上がりしています。二つ目は、物価上昇と値上げ。企業努力では吸収しきれず、価格転嫁も避けられません。三つ目は、賃金の伸び悩み。物価が上がっても収入が追いつかず、生活の余裕は生まれません。四つ目は、外需の不安定さ。地政学的なパワーバランスやトランプ関税など、国際的な不確実性が増しています。
これだけを見ると、企業にとっても生活者にとっても、未来は暗く見えてしまいそうです。
希望の芽は、意外と身近にある
しかしながら、そんな中にも、じっと目を凝らすと、小さな希望の芽は見えています。たとえば、「コメが高い」「不足している」といった現状の中でも、備蓄米をきっかけに新しい流通の動きが出てきそうです。まだ先行きは不透明ですが、これまでの仕組みに依存しない、新しい流通のはじまりにも見えます。
こうした変化の兆しを、「可能性」「希望」と見る目も、いま必要なのかもしれません。
モノの見方は、ひとつではありません

同じ出来事を見ても、人によって受け止め方は違います。「コメが高くて困る」と見るか、「国産のコメの価値が見直される機会」、またはコメの流通や食糧問題を具体的に解決していく入口と見るか。
ブランドも同じです。目の前の事実にどう意味を与えるか。その視点次第で、発信するストーリーも、顧客との関係性も変わってきます。
明るさは、無責任な楽観ではない
希望や明るさというと、楽観的で現実逃避のように思われることがあります。でも、そればかりではありません。「状況を正確に見たうえで、そこに可能性を見出そうとすること」。これは日々、私たちマーケターが取り組んでいることですね。私たちは楽観的にせよ、悲観的にせよ、状況を正確に把握し機会を見出す仕事をしています。それが、希望あるブランドの基本姿勢だと思います。
そして、いま求められているのは、「耐える力」だけでなく「進みたくなる気持ち」を与えてくれるブランドではないでしょうか。
希望を感じられるブランドでいましょう
いまのような時代には、機能や価格よりも「このブランドといると前を向ける」と思えることの方が、大きな価値になるかもしれないと思います。それは無理に希望を語るというより、日々のふるまいや言葉の端々に、未来へのまなざしがにじんでいるかどうかです。「変わる兆し」を見つけ、それを静かに伝えていくこと。希望を語るブランドは、決して世間を煽(あお)らず、でも確かに、選ばれやすくなっていきます。