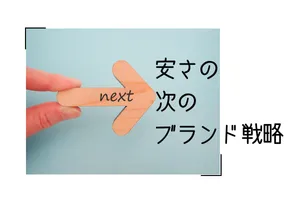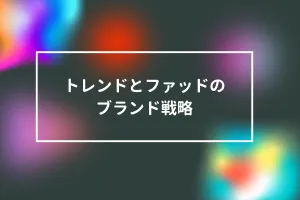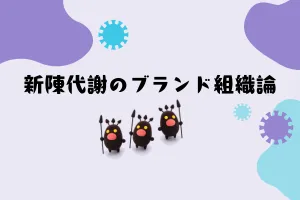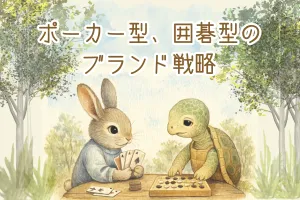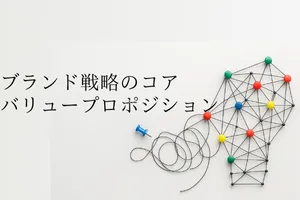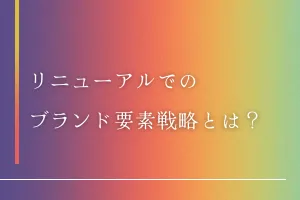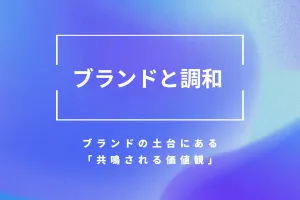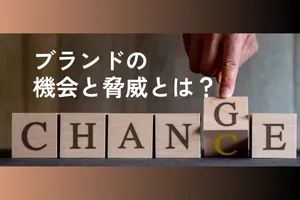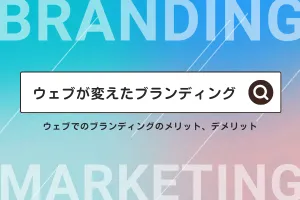“自社らしさ”で動くブランド組織
配信日:2025年11月19日
企業のなかで「ブランド」という言葉ほど、人によって解釈がバラつくものはありません。営業は「ブランド=売れる力」と捉え、デザイナーは「ブランド=世界観」と感じ、経営は「ブランド=コーポレイトイメージ」と考える。どれも間違いではありませんが、共通言語になっていないために議論がすれ違い、現場は混乱してしまいます。
この状態で「ブランドを強くしよう」と号令をかけても、誰も同じ方向を見ていない。だからこそ、必要なのは「ブランドリテラシー」を組織として底上げすることなのです。
リテラシーとは知識ではなく“感度”である
ブランドリテラシーを高めるというのは、単に知識を教えることではありません。それは「ブランドのらしさ」を感じ取る感度を磨くことです。たとえば、「この広告コピーはうちらしくない気がする」「この接客のトーンはブランドの世界観からずれている」と直感的に気づける人が増えれば、ブランドは自然と整っていきます。
ブランドは理屈ではなく、体験の整合性で感じられるものです。社員ひとりひとりがその整合性を判断できるようになってこそ、ブランドが生き始めます。
現場でリテラシーを上げる3つの方法
- 第一に、「ブランド判断を伴う会話」を増やすことです。
- 例えば広告会社との会議の中で、「この提案、うちらしい?」という問いを投げかけてみる。それだけでブランドを基準にした思考が生まれます。
- 第二に、「成功・失敗事例の共有」を日常化すること。
- 広告でも、店舗でも、商品開発でも、「どんな時にブランドらしさが伝わったか」をチームで話し合う。そうした具体例の積み重ねが、ブランドの基準をチームに刻みます。
- 第三に、「個々人がブランド体験を提供する機会」をつくること。
- 社員自身がSNS投稿や小さな発信を通じて、自分の言葉でブランドを伝えてみる。実践のなかで、ブランドは「自分ごと」になっていきます。
“守るブランド”から“活かすブランド”へ

ブランドリテラシーが高い組織は、ブランドステートメントに書かれたルールに縛られるのではなく、ルールの背後にある意図を理解しています。「ブランドを守る」とは、フォントやロゴの規定を厳守することではなく、「なぜそれがブランドらしいのか」を理解した上で、柔軟に表現を工夫できる状態のことです。つまり「守るために硬直する」のではなく、「らしさを活かして柔軟に動く」。それが本当の意味でブランドが生きている状態です。そういう意味ではブランドステートメントとは議論の土台でもあります。
最終的に、ブランドリテラシーは組織文化そのものになるでしょう。経営者から現場スタッフまでが共通の感じ方を持ち、日々の判断や会話の中にブランドが息づく。そんな組織は、どんな変化の時代でも一貫性と柔軟性を失わないでしょう。そしてその結果、ブランドは「語られる存在」から「生きる基盤」へと進化していくでしょう。やがて社員ひとりひとりの感度と判断が積み重なり、ブランドは企業の意思を動かす力へと変わっていくのです。