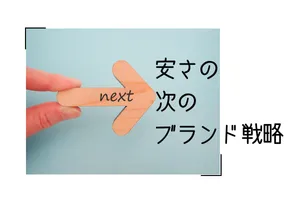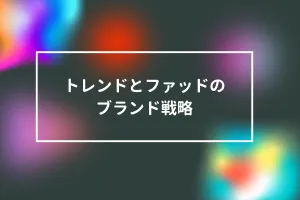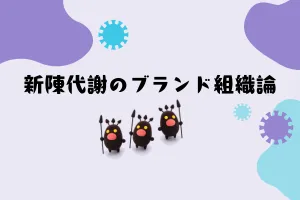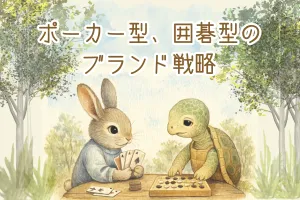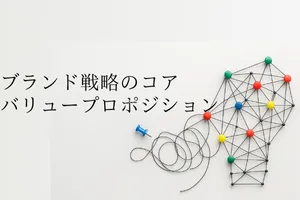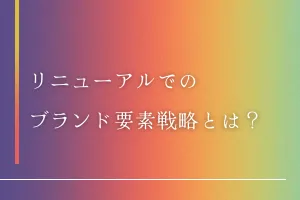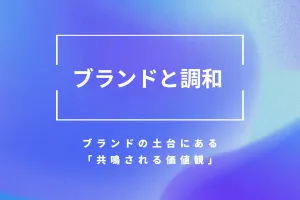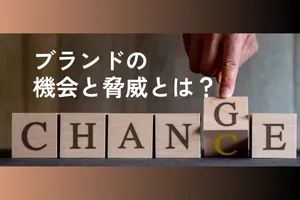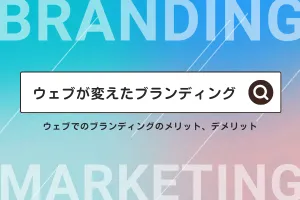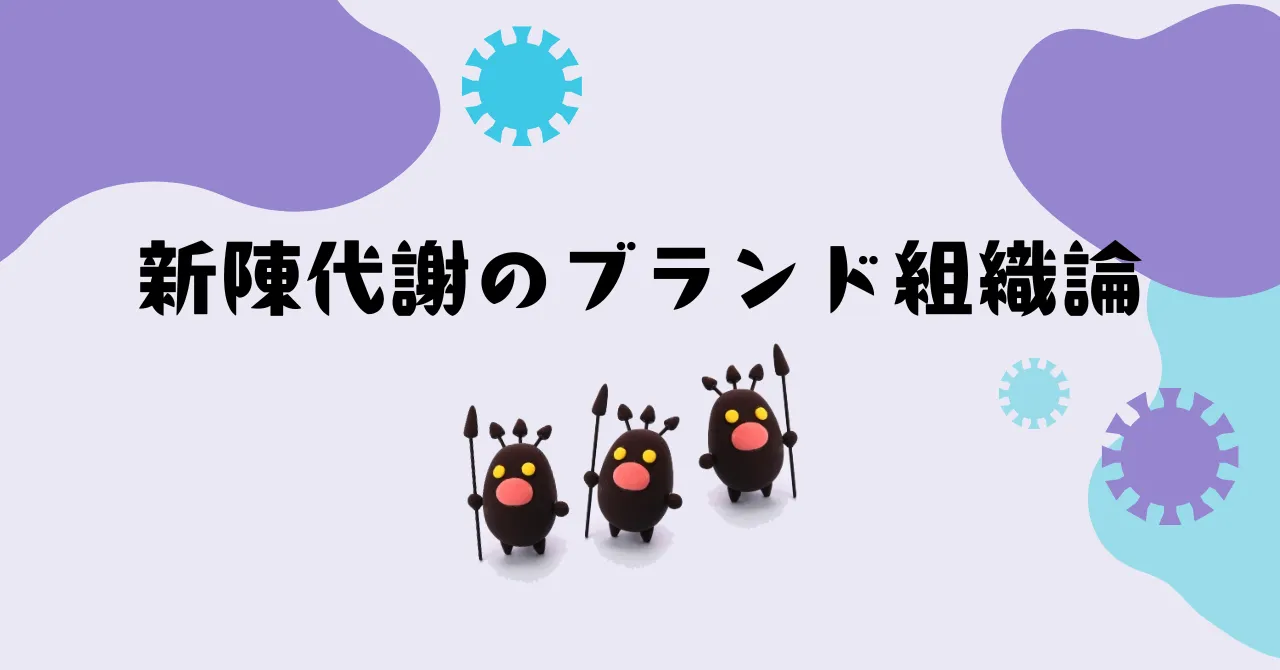
新陳代謝のブランド組織論
配信日:2025年11月12日
高市早苗氏が日本初の女性総理に就任し、支持率が70%を超えるというニュースは、単なる新総理登場以上の意味を持っています。これは、長く続いた「男社会的な秩序」や「世襲や慣習による秩序」の更新を社会全体が求めていることの表れです。変化の本質は、新しい時代の文脈に適応することにあります。けれど、組織(特に古い組織)は往々にしてこの適応、つまり「新陳代謝」を避けようとします。なぜなら、変化には痛みが伴うからです。しかもその痛みは「悪」ではなく「善意」の中に潜んでいることが多いものです。
抵抗勢力は、悪意のない“過去の正義”でできている
どんな組織にも、変化に抵抗する人たちがいます。けれど、彼らは決して悪意を持っているわけではありません。むしろ彼らは、かつての成功を支え、組織を守り抜いてきた普通のひとびとです。彼らの根底には、「今のやり方が最善だ」「現場を混乱させたくない」「顧客を失いたくない」という責任感があります。つまり抵抗とは、「変化を恐れる防衛反応」というよりは「過去の正義の延長」と定義してよいのではないでしょうか。だからこそ改革を推し進めるミッションを抱くもの(新任社長など)は改革そのものに迷い、時に躊躇するのです。
改革者が彼らを「古い」と切り捨てた瞬間、組織の血流は止まります。よって本当の難しさは、悪ではなく善に守られた「惰性」をどう動かすかにあります。組織の新陳代謝とは、この「善意の壁」にどう向き合うかという問題なのです。
ガースナーが示した、“土俵を変える”という知恵
1993年、崩壊寸前だったIBMにやってきたルイス・ガースナーは、まさにこの善意の抵抗に直面しました。社内には「われわれは技術の会社だ」「ハードウェアこそIBMの魂だ」という信念が根深く残っており、それはIBMの誇りそのものでした。彼らはIBMの敵ではなく「忠誠心の化身」だったのです。
ガースナーはその誇りを正面から否定せず、「土俵を変える」という手法を取りました。つまり、抵抗勢力の議論の土台に乗らず、まったく別の基準、「顧客価値」という新しい正義の上に議論を移したのです。
彼はこう語っています。「技術そのものではなく、顧客の問題を解決することが唯一の正義だ」。つまり、部門ごとの最適化ではなく、顧客の課題を解決する力を会社全体で追求する仕組みに変え、報酬・評価制度・意思決定をすべて顧客基準に再設計しました。結果として、古参の社員は古い論理(技術・ハードウェアこそIBMの魂)では戦えなくなった。彼らは排除されたのではなく、新しい土俵に立たされたのです。
善意の抵抗を越えるために
組織の新陳代謝を止めるのは、怠惰ではなく「忠誠」だと思います。「これまでのやり方で十分やってこれた」という自負。「変えるより守るほうが安全だ」という責任感。それらは組織にとって必要な栄養でもあります。
けれど、どんなに善意に満ちていても、その栄養が代謝を止めることがある。だからこそリーダーは、善人を敵に回すのではなく、土俵を変えることで彼らを味方に変える必要があります。新しい正義を示し、「その善意が次の時代でも生きる場」を作ること。それが、組織を若返らせる唯一の方法です。
痛みを恐れず、正義を更新せよ
新陳代謝とは、ガースナーが示したように正しいか間違っているかの議論を超え、「今、何を基準に生きるか」と土俵を変えることです。それこそが、ブランドや組織における新陳代謝の考え方なのです。正義は時とともに少しずつ古びていきます。だからこそ、それをもう一度「今に通用するかたち」へと呼び戻すことが大事だと思います。