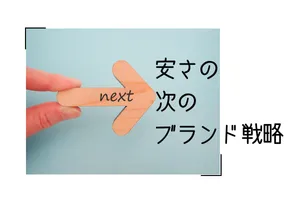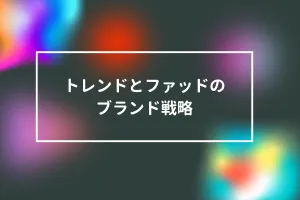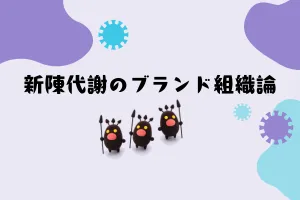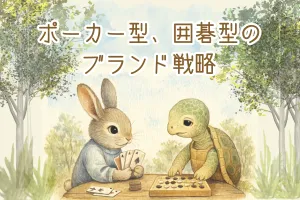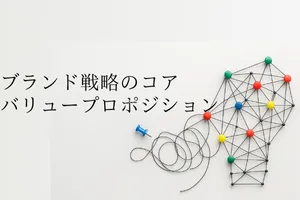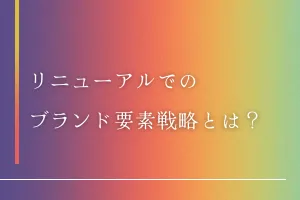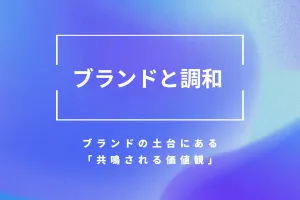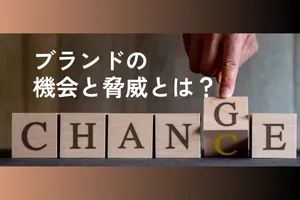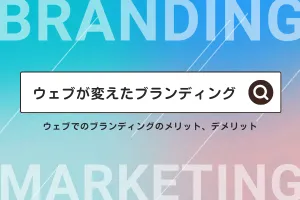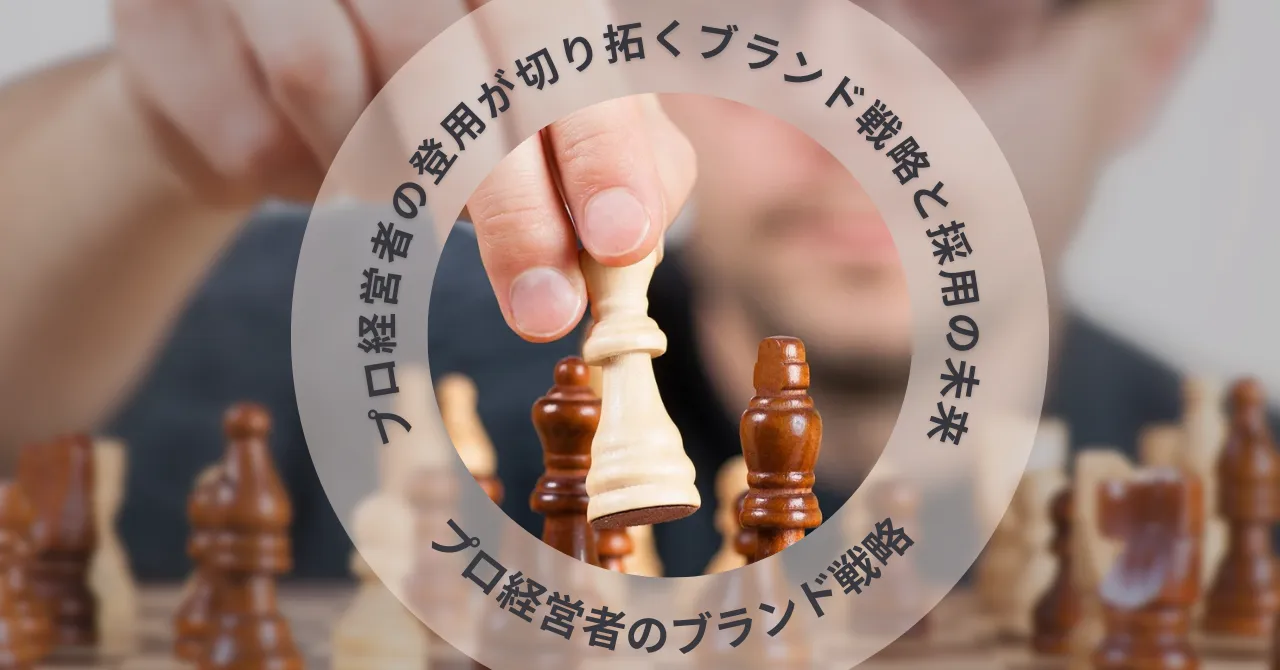
プロ経営者の採用・登用が切り拓く日本企業のブランド戦略【プロ経営者のブランド戦略】
配信日:2025年8月27日
経営がきりもみ状態に陥るとき、または企業が経営危機に直面したとき、内部人材の延長線上だけでは立て直しが難しい場合があります。社内の論理や慣習に縛られ、抜本的な改革に手をつけられないからです。特に日本の超大手企業では、承継の不全や文化の硬直が壁となり、内部からは再生の突破口を見いだせないことが少なくありません。
内部承継の限界が露呈した東芝
その典型が東芝です。粉飾決算問題、原子力事業の迷走などに対して、歴代の内部昇格組は「先送り」と「責任回避」で乗り切ろうとしました。結果として真の改革は進まず、外資ファンドに解体される流れを止めることができませんでした。ここに見えるのは、内部人材が抱える「聖域に切り込めない構造的な弱さ」です。
外部人材による立て直しの成功例
一方で、外部人材が企業を蘇らせた例もあります。日産に迎えられたカルロス・ゴーン氏(かつての功績として)は、系列や工場閉鎖といった聖域に踏み込み、赤字から黒字への転換を果たしました。JALでは稲盛和夫さんが未経験の航空業界に入り、「哲学」と「人心掌握」で社員意識を変え、V字回復を実現しました。
資生堂では魚谷雅彦さん、日本コカ・コーラでマーケティングを率いた経験を持つプロ経営者が就任しました。当時の資生堂は、国内依存の構造と百貨店依存の販売モデルが限界に達しつつありました。魚谷さんはそこで「ブランドの再定義」に踏み込みました。資生堂を単なる化粧品メーカーではなく、「美の文化を世界に届けるブランド」として位置づけ直したのです。(日経新聞2025年7月度:私の履歴書より)
具体的には、プレミアム領域に経営資源を集中し、グローバルで戦える「SHISEIDO」ブランドを再構築。国内での縮小均衡から脱し、世界のラグジュアリーブランドと肩を並べる存在へとブランドイメージを高めました。これは単なる販売戦略の転換ではなく、社員一人ひとりが「自分たちは美の価値を世界に提供するブランドを担っている」という誇りを取り戻すプロセスでもありました。
なぜ内部人材では改革できないのか
もちろん、上手くいくケースもあります。しかしいくつかの事例を俯瞰すると、内部人材が改革を実行できない背景にはいくつかの要因があるようです。
- 系列・労組・OBといった利害関係のしがらみから自由になれない。
- 同じ文化で育ったために「聖域」を聖域と認識できない。
- 強力なトップの下で後継者が育たず、独自の判断軸を持てない。
このように、内部承継は安定感をもたらす一方で、危機の場面では組織を縛る要因になってしまうようなのです。
プロ経営者の役割
では、外部から迎えられるプロ経営者の役割とは何でしょうか。彼らは、組織に新しい文法を持ち込み、次を育てる仕組みを設計する存在と思われます。短期的に業績を改善するだけでなく、リーダーシップのサイクルを残すことで、企業を持続的に成長できる状態へと導きます。
また彼らの戦略は「俺がやる」ではなく「俺の次を育てる」という姿勢に集約されるようです。そして社員や得意先、生活者といった生命線を再び強く結び直すことで、組織に新しいブランド価値を生み出すのです。つまりブランドを再定義し、その価値を組織全体に浸透させる。これこそがプロ経営者のブランド戦略であり、日本企業が持続的成長を取り戻すための条件なのです。