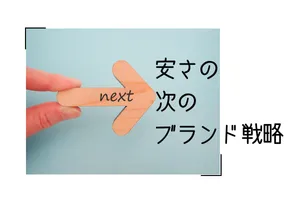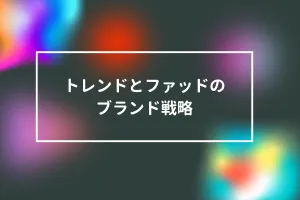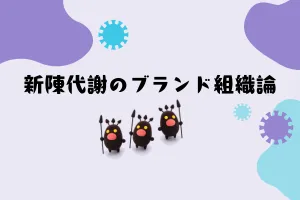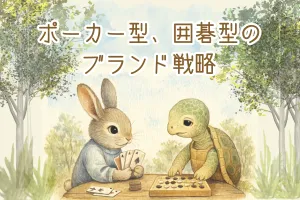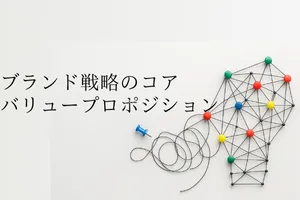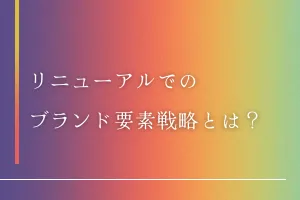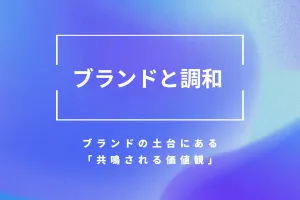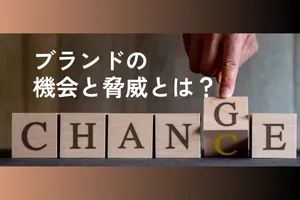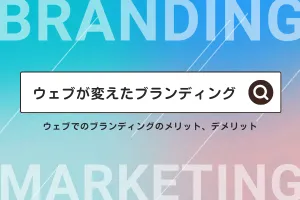生活防衛モードのブランド戦略
配信日:2025年8月6日
いまの店頭は、値引き、クーポン、まとめ買いであふれています。物価高と将来不安の中で、生活者は生活防衛モードに入り、企業もそれに応えて価格訴求を強めてきました。
でも、どこか引っかかります。値段を下げるだけで、本当に生活者の心に届いているのか。「何かが足りない」感覚が残ります。
ブレンディ198円、ネスカフェ178円の衝撃
私には忘れられない光景があります。東日本大震災のあと、スーパーの棚で、ブレンディスティックが198円、それに対してネスカフェエクセラのスティックコーヒーが178円で売られていました。
世界的ブランドのネスカフェが国産ブランドより安い。その瞬間、私は驚き、そして考え込みました。当時、マーケティングのバズワードは「貧困層マーケティング」。特にネスレのようなグローバルブランドは、アフリカなど新興国市場で低所得層市場に製品を届ける戦略を磨いていました。
ネスレのPPP戦略と自尊心の設計
ネスレはこうした市場向けの製品戦略をPPP(Popularly Positioned Products)と呼びます。 これは単なる低価格商品ではなく、
- 価格は手が届くレベルに抑える
- 品質や栄養は十分に担保する
- パッケージや見た目も「誇りを感じられる」ものにする
という構造で成り立っています。
つまり、「安くてもネスレは自分にふさわしい」という小さな誇りを提供する戦略なのです。「ブレンディ198円 vs ネスカフェ178円」も単なる安売りではなく、心理的価値を設計した価格戦略だった可能性があります。つまり消費者は「安い」という満足感を得られるのみならず、「ネスカフェ」でしかるべき自尊心を保つことができるわけです。これがPPP戦略の本質だと思います。
生活防衛モードにおけるブランドの役割
日本の現状を振り返ると、値下げ中心の施策は確かに合理的です。ここに生活者の自尊心という視点が加わると、もっといいだろうと思います。生活者は、ただ安いから買うだけでは心が満たされません。そこに「選んだ自分を肯定できる理由」があると、より買いやすいのです。
- 安さに加え、誇りを感じるブランド体験を届ける
- 節約の中にも、ちょっとしたプライドを残す
これこそが、生活防衛モードの時代にブランドが果たすべき本当の役割かもしれません。値段だけで勝負するブランドは一時的に選ばれても、それだけのことかもしれません。
「値段は財布を動かす。自尊心が心を動かす」

この言葉は、生活防衛モードの時代をキーワードかもしれません。生活者は、出費を減らすために価格を見ています。でも、買い物の満足はお金だけでは得られない。財布は価格で動きますが、「選んだ自分に少しの誇りを感じられること」が、リピート購入やブランド愛着の源泉になる。安さの奥に潜む心理的価値の設計が、これからのブランド戦略には欠かせません。