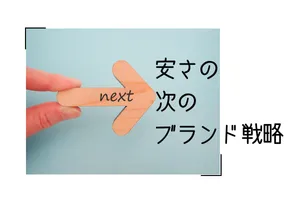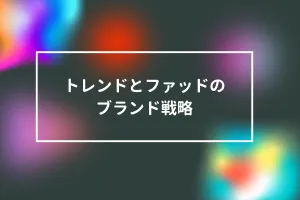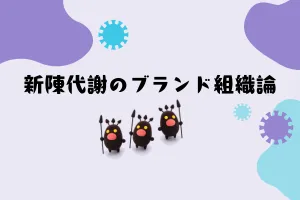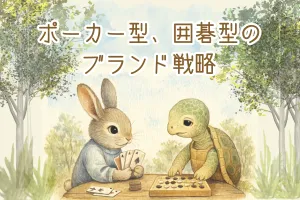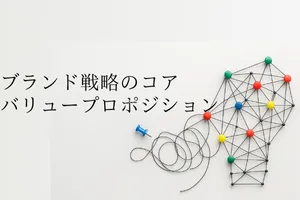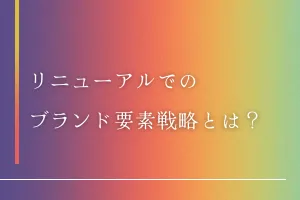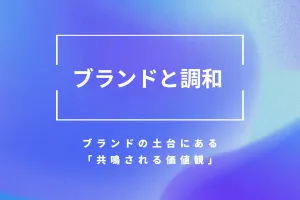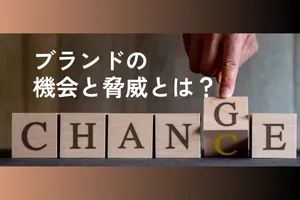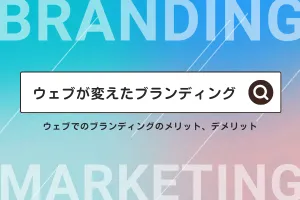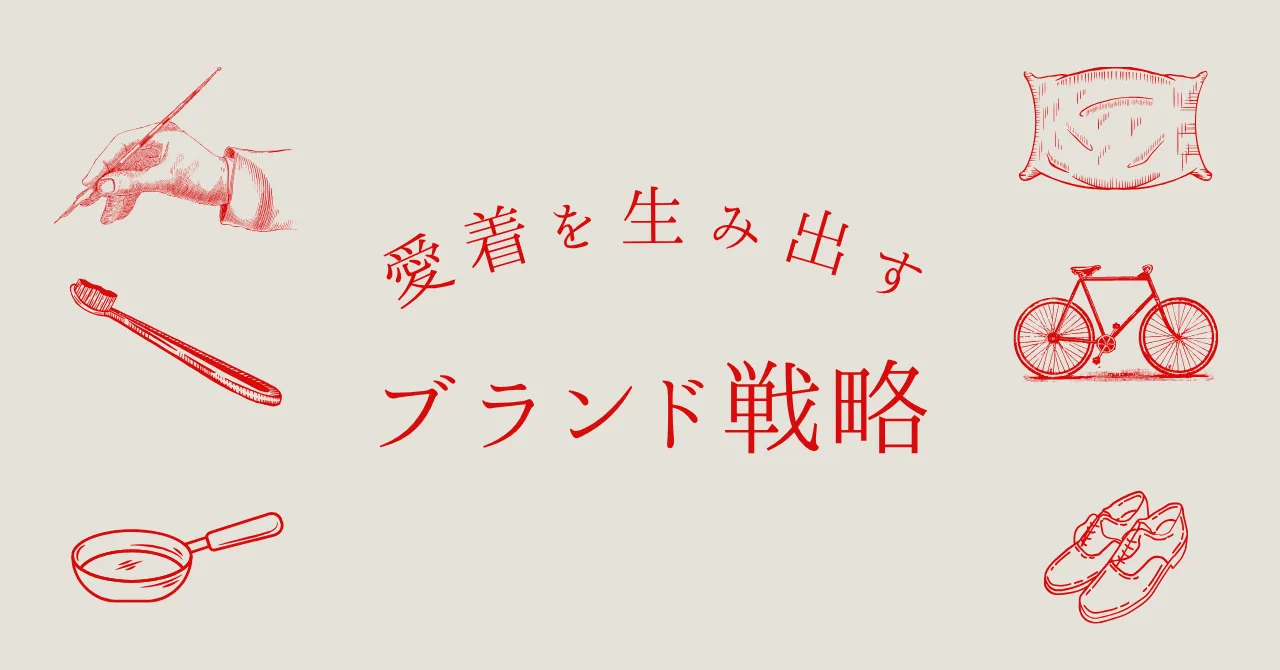
愛着を生み出すブランド戦略
配信日:2025年7月30日
ブランド戦略では「好きになってもらう」ことが大事だとされています。でも、私たちが実際に日々接しているモノやブランドとの関係を振り返ってみると、「好きじゃないけど、使っている」「別に期待してなかったけど、気づけば手放せなくなっていた」。そんな経験のほうがむしろ多いのではないでしょうか。実際、そうしたモノとの関係のほうが、案外リアルだったりしませんか?
「好きではないが使っている」と「好きで使っている」
このテーマを考えるうえで、ふと頭に浮かんだモノが二つあります。一つ目は、高校時代に父から与えられた自転車です。無骨なデザインで、重量もあり、こぐのがとにかく大変でした。さらにブレーキをかけると「ガクッ」と変な衝撃がくる。正直、好きだと感じたことは一度もありません。しかし高校3年間、私はこの自転車で通学していました。「好きではないが使っている」好事例です。
「好きで使っていた」ものの代表は、バロン・フィリップ社(5大シャトーの1つ)の景品のワインオープナーです。こちらはいまでも使っています。特に使い勝手がどうとか、感触が良いとかではありません。オープナー自体は、ごくありふれたデザインのものです。ところが、その持ち手部分に、ムートンカデ(バロン・フィリップ社のテーブルワイン)のロゴが小さく入っていたのです。「5大シャトーでも景品をつけるのか」という素朴な違和感が我ながら面白くて、そしてそれが妙に気に入って、以来20年以上、ずっとそればかり使い続けています。いまではロゴもすっかり消えてしまいました。
毎回ワインを開けるたびに、その手触りにちょっとした満足を感じます。金属のくすみや無数にある細かな傷も、むしろ味わいです。これは、まさに「好きで使っている」モノだといえます。
自転車とワインオープナー。どちらも長年使い続けてきたモノですが、関係のスタート地点はまるで違いました。自転車は、「好きではないが使いはじめた」。ワインオープナーは、「好きで使いはじめた」。どちらが良い、悪いという話ではありません。けれどこの違いには、ブランドと人との関係性を考えるうえで重要な示唆があるように思います。
なぜ、好きじゃなくても使い続けるのか?
この2つを通して見えてきたのは、使うかどうかは「好きかどうか」だけでは決まらないということです。以下のような条件が、使うかどうかの分岐点になっているように思います。
- 自分の意思で選んでいるかどうか
- 与えられたものでも、「使う」選択を自分でしたとき、そこには微細ながらも“関与”が生まれます。(自転車は嫌々ながら当てはまる。)
- そのモノとともに過ごした「時間」や「記憶」があるか
- 日常の中で一緒に過ごした時間。雨の日の通学、遅刻ギリギリの坂道。あるいは誕生日の夜に開けたワイン。そうした記憶の積層が、モノに意味を与えていきます。(どちらにも当てはまる。)
- 自分の価値観や美意識と、どこかでつながっているか
- ワインオープナーのくたびれ具合が、なぜか自分の感覚にしっくりくる。それは自分と、どこかで共鳴しているからかもしれません。(自転車には当てはまらない。)
自転車の「その後」
けれど、その先があります。実は、好きじゃなかったその自転車を、私は大学に進学して東京で生活するようになっても、そして社会人になって大阪に赴任しても、引っ越しのたびに一緒に持ち運び、新しいものに買い替えることなく、ずっと使い続けていました。好きじゃなかったけれど、捨てられなかった。なぜか。それはきっと、「愛着」があったからです。そして最後に手放すときには、少し寂しさを感じた。それはもう、好きを超越した感情だったのだと思います。
ブランドが目指すのは、ただ「好きです」と言われる存在になることではなく、長く、静かに、生活の中に根を張っていくような存在になること。そこにこそ、愛着を生み出すブランド戦略の本質があるのではないでしょうか。